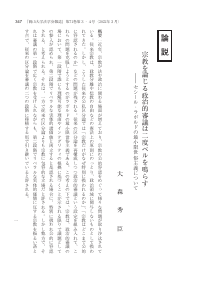Okayama Law Journal
Published by The Association of Law of Okayama University
Permalink : http://escholarship.lib.okayama-u.ac.jp/63452
Political Deliberation over Religion Rings Twice ―On Cécile Laborde’s Minimal Secularism
Published Date
2022-03-18
Abstract
近年、宗教が法や政治に関わる場面が増えており、宗教の公的容認をめぐって様々な問題が取り沙汰されている。従来宗教は、政教分離や信教の自由などの憲法上の原則にのっとり、政治領域に関与しないものとして扱われてきた。しかし、こうした従来の公私区分論では「宗教だけがなぜ特別に扱われるのか」、「宗教はどこまで公的に容認されるのか」などの問題が残される。従来の区分論を再構成しつつ政治的審議という設定を組み入れて、これらの問題を克服しようとするのがラボルドの最小限世俗主義である。この考えの下では、宗教は、政治的審議の場において、第一段階で誰にも理解可能な理由やインテグリティの根拠に基づくことが示される限りで議題としての参入が認められ、第二段階でリベラルな実体的諸価値と両立すると是認される場合に、特別に扱われ公的に容認される、と考えられる。それは、一方で従来の区分論よりも宗教に包容的な立場だと評される。しかし他方で、それは審議の第一段階で広く宗教を受け入れながらも、第二段階でリベラルな実体的価値に反する宗教を振るい落とす点で、従来の区分論を審議の二つの段階に移植する形で引き継いでいると評される。
Note
論説 (Article)
ISSN
0386-3050
NCID
AN00033040